円空の残した謎が解けた!
一人二役「分身」が明らかに
円空の名はよく知られている。旅に明け暮れした遊行僧、十二万体造像の悲願を立てた彫り師、あるいは現代人の心を引きつけてやまない芸術家。円空に関する本も多く出版されている。
しかし、それらのほとんどは円空仏にまつわる本で、円空その人の生き方や目指したものをテーマとした著作となると少ない。いまだに謎に包まれたままの人物であり、それどころか誤解されているものもある。著者はこうした謎の解明に挑み、通説ではあり得ない意外な結論にたどり着いた。
それはキリスト教との結び付きだった。円空の生きた当時は厳しい切支丹禁制下にあり、尾張では数千人が斬首されている。これら犠牲者の霊や残された家族・縁者らを慰めようと密かに分身をつくり、キリスト教徒らを擁護する活動をしていたというのだ。
この結論に至るまで、研究は困難を極めた。著者は各地を訪ね歩いて円空の残した仏像・神像や文書・和歌・漢詩・経典などに当たり、これまでに出された類書も読みあさった。そうした中から円空は禁令を犯さないよう巧に工夫し、多くの謎かけをし活動していることが明らかになった。
ここに至る謎解きの過程が面白い。謎が解けてくると円空の目指していたもの、行動や生き方までもが明らかになってきた。これは円空の見方を変える、これまでにない円空論と言える。
A5判・192頁・1500円+税
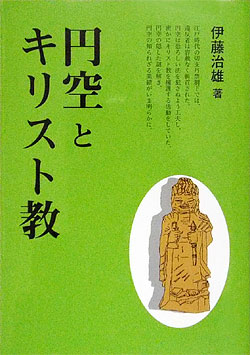 も・く・じ
- 第1章 数字や判じ物による洒落と謎かけ
-
1、数学を使った洒落と謎解き遊び
- 2、江戸時代に流行った数学と洒落
- 3、判じ物や語呂合わせも盛んに活用
- 第2章 近江商人と北前船
-
1、近江商人はいつから松前へ行くようになったのか
- 2、円空時代の切支丹政策――尾張藩を中心として
- 3、切支丹と円空の関係
- 第3章 北海道・東北における作仏旅行の足跡
- 1、青年期(30歳台前半まで)の円空
- 2、いつの時代に、どこを旅したのか
- 3、円空はなぜ松前・青森へ旅をしたのか
- 4、 津軽藩の日記に残る円空の足跡
- 第4章 片田と立神での大般若経の修理
- 1、三重県志摩で円空は何をし、何を考えたか
- 2、二つの経典に残された心の変化の跡
- 3、二つの和歌が示す意味の違い
- 4、万人を取り込む和歌の完成、歓喜沙門の誕生
- 第5章 千面菩薩の創作の目的は何か
- 1、創作した千面菩薩の姿と形
- 2、厨子の文字に隠されたもの
- 3、ここに言う「護法」とは何か
- 4、二体の自刻像「護法神像」は何を表すのか
- 5、乙護童子は何を語ろうとしているのか
- 6、乙護童子像が明かす事実
-
第6章 羽島市中観音堂の十一面観音は千面菩薩
- 1、十一面観音の制作時期とその像様
- 2、千面菩薩を証明するもの
- 3、一人三役の円空、仏性常住金剛宝戒相承血脈
-
第7章 飛騨千光寺の両面宿儺と男童子
- 1、円空の彫った両面宿儺の由来
- 2、男童子とは誰のことか
- 3、「心の分身」の真像
-
第8章 伊吹山の観音像は何を物語るか
- 1、近江の人へ残した感謝の和歌
- 2、千面菩薩の効果を記す漢詩だった
- 3、「心の分身、円空」の終業
-
第9章 千面菩薩の素性を明かす金木戸観音堂の諸像
- 1、今上皇帝の背銘の読み解き
- 2、円空作の十一面観音には千面菩薩もある
- 3、円空はなぜ今上皇帝に終了報告をしたのか
- 4、円空の徳音が意味するもの
-
第10章 円空はなぜ入定の道を選んだのか
- 1、高賀神社における入定の準備
- 2、円空の入定の意義は何か
- 第11章 「心の分身」の活動と意義
- 1、千面菩薩の創作と護法の布教
- 2、千体仏供養の業績――無名沙門の功績
- 3、キリスト教に関する円空の業績は何か――正論の青山論文
-
第12章 〈補遺〉十護童子発見による謎解きの再検討
- 1、十護童子の発見
- 2、十護童子はいつ・どこで生まれたか、乙護童子の関係
- 3、歓喜沙門と観喜沙門の間
-
〈付録〉
- 1、切支丹禁制の制度用語
- 2、青山玄「円空造仏の動機について」
- 3、冊子「円空研究」の発行実績
- 4、参考文献
- あとがき
|


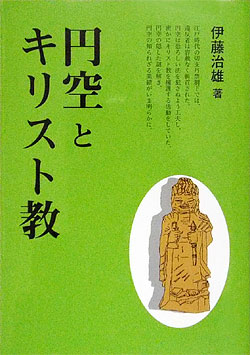
![]()